こんにちは、tekowaです。
私は現役保育園栄養士で、保育補助も経験、他にも介護福祉士やベビーフードインストラクター、幼児食マイスターの資格を持っています。
そんな私がすき家の異物混入問題について多角的に考察していきます。

すき家の異物混入問題概要
すき家で発生した異物混入問題の概要は以下の通りです。
1件目の事案(ネズミ混入):発生時期: 2025年1月21日
場所: すき家 鳥取南吉方店(鳥取県鳥取市)
内容: お客様に提供された味噌汁の中にネズミの死骸が混入。
経緯:お客様からの指摘で発覚。
すき家は3月22日に公式サイトで謝罪し、調査結果を公表。
混入原因は、店舗の冷蔵庫のパッキンのひび割れからネズミが侵入し、味噌汁の具材を入れたお椀を冷蔵庫で一時保管していた際に混入した可能性が高いと結論付けられました。
2件目の事案(ゴキブリ混入)
発生時期: 2025年3月28日
場所: すき家 昭島駅南店(東京都昭島市)
内容: お客様が購入した弁当にゴキブリの一部が混入。
経緯:お客様からの電話で判明。
当該店舗は自主的に営業を停止し、専門業者による駆除作業を実施予定。
ゼンショーホールディングス(すき家の親会社)の対応:上記2件の異物混入事案を受け、ショッピングセンター内などの一部店舗を除く全国のすき家店舗を、2025年3月31日から4月4日まで一時休業。
全店で清掃や害虫駆除対策、従業員への衛生指導を徹底するとしています。
再発防止策として、商品提供前の目視確認の徹底、従業員への衛生教育の定期実施、建物点検と修繕、廃棄物保管庫の冷蔵対応化、清掃時間の確保などの対策を発表しています。
まさか大手チェーンで短期間に2度も異物混入があるとは思いませんでしたよね。
私もとても驚きました。
日頃、私は1歳~6歳までの子どもたちの食事を作ったり、0~2歳児の保育補助をしています。
また、プライベートでは2児の母なので、食の安全にはとても敏感になっています。
なので今回は、食の安全について、栄養士、介護福祉士、保育補助の視点から解説していこうと思います。
【栄養士視点】大量調理の現場から見る、すき家の衛生管理体制への疑問と再発防止への期待
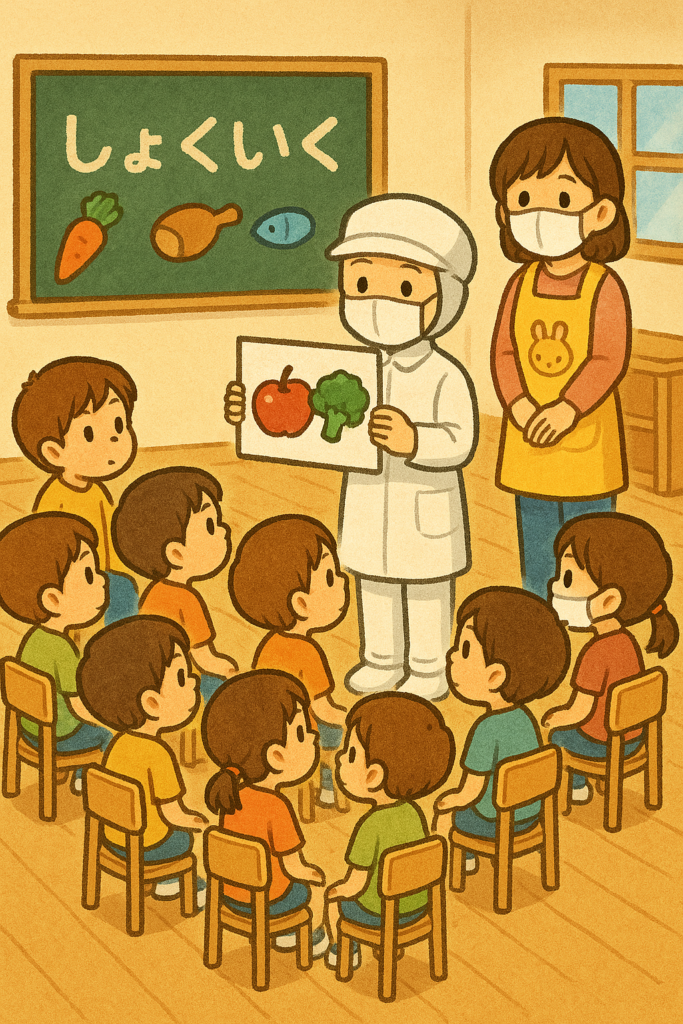
保育園などの大量調理をする現場では、食材を受け取る場所、野菜の皮をむき洗う場所、食材を切る場所全てが決まっています。
それだけでなく、生卵を割る場所や割り方1つまで事細かく決められています。
今回混入した動物や昆虫の死骸に関することで言えば、毎月消毒の専門業者さんが訪れ、昆虫が罠にかかっているか、動物が侵入できるような劣化がないかを調べに来てくれます。
動物が侵入しそうな経路があれば、写真に収めてみせてもらったり、実際に見せてもらい、穴を塞いだり掃除をして未然に防ぎます。
すき家は大手チェーン、大量調理現場ですのでこのような対策が十分に講じられていなかったとすれば、問題視されるべき点でしょう。
『全店で清掃や害虫駆除対策、従業員への衛生指導を徹底する』事で二度と異物混入がないことを祈るばかりです。
再発防止策として、商品提供前の目視確認の徹底、従業員への衛生教育の定期実施、建物点検と修繕、廃棄物保管庫の冷蔵対応化、清掃時間の確保などの対策を発表していますが、これは妥当だと思います。
再発防止のためにも、定期的な勉強会なども実施されるとより良いと感じました。
【保育補助・幼児食マイスター視点】乳幼児を外食させるのに便利なすき家、信頼回復はできるのか?

私は現在、保育園栄養士の仕事の傍らで、0~2歳児の保育補助もしています。
保育園に通うの子どもたちにとって、親御さんが料理という時間をお金で買って外食することでコミュニケーションの時間が取れますし、共働き家庭ですと、食事を作らなくて良いのですき家などのテイクアウトできるチェーン店は、コスパが良く利用したくなりますよね。
すき家は私もよく利用しています。
我が家は長女5歳次女2歳なのですが、長女はお刺身好き次女は肉好きな姉妹なので、メニューが豊富で価格帯も1人800円もあればどちらも満足できるので重宝するためです。
今回の異物混入で、私は驚きと落胆が隠せませんでした。
だってまさか、子どもたちも大好きなすき家でこのような信じられない事態が起こるとは夢にも思いませんよね!?
保育園では、子どもたちの口に入るものは、本当に細心の注意を払って調理・提供しています。
異物混入などあってはならないことであり、もし起きてしまった場合の責任の重さを常に感じています。
その意識があるからこそ、今回の事件には強い衝撃を受けました。
保育現場では、保育士や子育て支援員、保育補助の皆で力を合わせ、外から石や木の枝、ダンゴムシなどの虫が食事の席に持ち込まれないように細心の注意を払っています。
ご飯前には手を洗い、アルコールで消毒し、食中毒防止にも配慮しています。
保育園での安心安全な食は、子どもたちに関わる保育士、子育て支援員、保育補助の努力の上に成り立っているのです。
そんな中、ネズミやゴキブリの一部が給食に混入していたらどうでしょうか?
特に、小さな子どもたちは、大人が思う以上に食べ物に異物が混入していることに気づきにくいものです。
もし、子どもがネズミやゴキブリの一部を口にしてしまったら…想像するだけでゾッとします…。
親としては、外食は手軽で便利な反面、子どもの安全には常に気を配っています。
今回の事件は、これまで以上に外食に対する不安を掻き立てるものとなりました。
5歳の長女は、ちょっと自分の嫌いな物や、魚のほぐし身に魚の骨が入っていようものならと「これなぁに?」と目くじらを立てるタイプですが、2歳の次女にはまだそれができません。
保育補助でこどもたちの食の安全を守っている身としても、幼い子どもを育てる親としても、すき家には、今回の事態を真摯に受け止め、二度とこのようなことが起こらないよう、徹底的な対策を講じていただきたいと強く願います。
そして、その対策の内容を、私たち子育て世代にも分かりやすく丁寧に説明してほしいと思います。
信頼を取り戻すためには、透明性のある情報公開が不可欠です。
【介護福祉士視点】加齢によるリスクと外食の選択 – 高齢者の食の安全を守るために
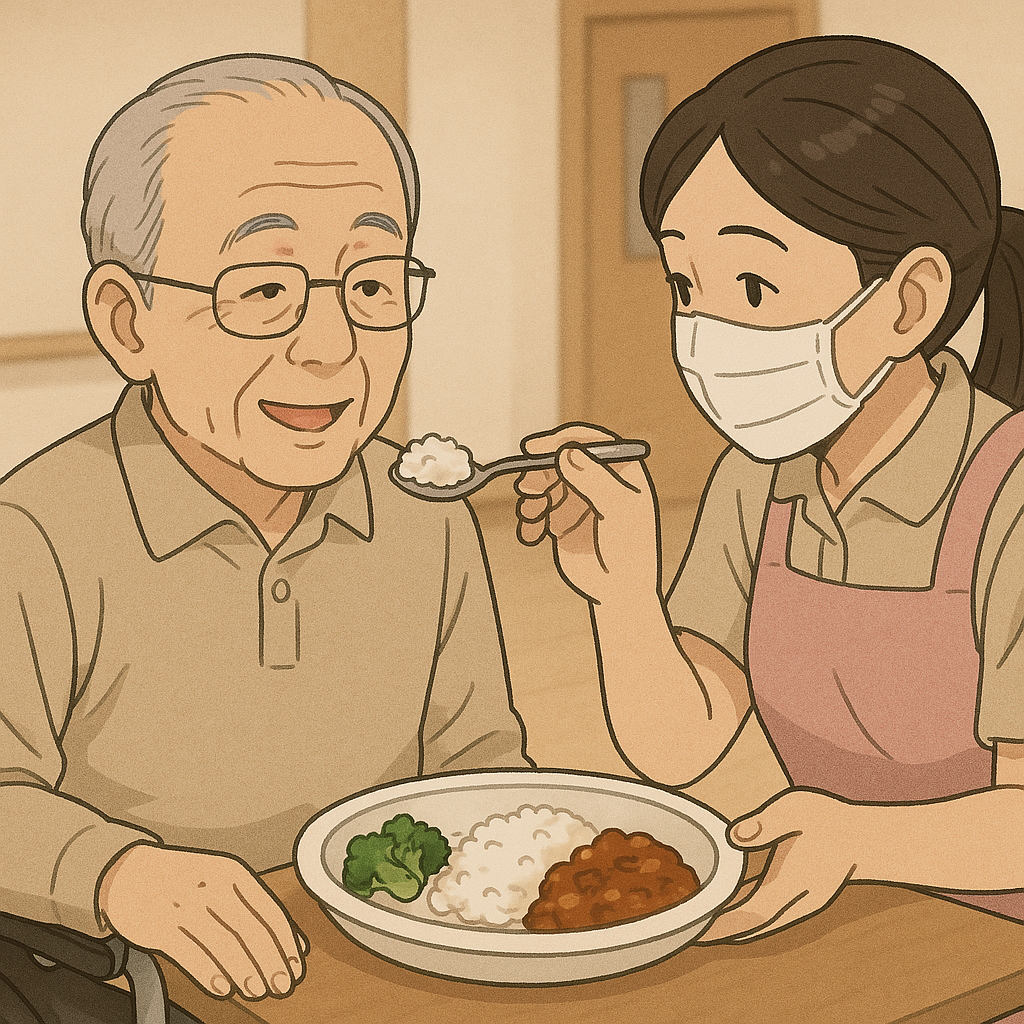
保育の現場で子どもたちの食の安全を守る重要性を痛感していますが、私がもう一つの専門とする介護の現場においても、食事は生活の質を大きく左右する要素です。
加齢に伴い、高齢者の方々は免疫力や消化機能が低下していることが多く、抵抗力が弱まっている場合があります。
そのため、食品に異物が混入した場合、健康に深刻な影響を及ぼす可能性が高くなります。
また、嚥下機能が低下している方にとっては、異物が気管に入り込み、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクも懸念されます。
それに、もし認知症患者が異物混入した食べ物を提供されたらどうでしょうか?
認知症患者は、判断力の低下が見られます。
認知機能が著しく低下していたら異物を異物と認識できずに口に入れてしまいます。
それが嚥下機能が低下している方だったらどうなるでしょうか?
前述の通り、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
介護の現場では、異物混入が命取りになることがあります。
そのため、保育施設と同じように、栄養士や調理員が衛生管理に気をつけて作った献立を、テーブルをアルコールや次亜塩素酸で拭いて清潔を保ちながら食事提供をしています。
食事形態も看護師、介護職員、言語聴覚士、医師、ケアマネージャーが連携をとり、一人一人にあった食事形態で提供されています。
今回の事件は、子どもから高齢者という幅広い世代に親しまれているすき家の、代表的なメニューである味噌汁に異物混入が発生したことで、非常に衝撃的でした。
もし自分の親が介護が必要になり、嚥下困難があって異物を口に入れて誤嚥性肺炎になったら…認知症で認知機能が低下し、異物を口にしてそれが有害なものだったら…
リーズナブルな価格で質が高く、豊富なメニューとサイズ展開の多さに定評のあるすき家には、心を入れ替えて衛生管理の徹底をしてほしいものですね。
まとめ
今回のすき家における異物混入問題は、それぞれの専門分野の視点から、改めて食の安全に対する意識の重要性を私たちに突きつけました。
『栄養士の視点』からは、保育園などの徹底した衛生管理と比較することで、大手チェーンにおいても同様の、あるいはそれ以上の厳格な管理体制の構築が不可欠であることが明確になりました。
再発防止策として提示された内容は妥当であると考えられますが、その実効性を高めるためには、定期的な研修や勉強会の実施が望まれます。
『保育補助の経験』からは、特に小さな子どもたちが異物を認識できないリスク、そして保育現場でいかに細心の注意を払って異物混入を防いでいるかを考えると、すき家においても提供前の徹底的なチェック体制の構築が急務であると感じます。
『介護福祉士の視点』からは、免疫力や認知機能、嚥下機能が低下した高齢者にとって、異物混入は生命に関わる重大な事故に繋がりかねないことが改めて認識されました。
介護現場での徹底した衛生管理と同様の意識で、すき家にも高齢者が安心して食事を楽しめる環境づくりを強く望みます。
『消費者』としては、今回の事態を真摯に受け止め、二度とこのような事態を引き起こさないための徹底的な対策をすき家には強く求めます。
リーズナブルな価格と豊富なメニューは魅力的である一方、安全性が損なわれては意味がありません。
信頼回復のため、企業努力を惜しまず、安心安全な料理を提供していただきたいと思います。
今回の事件は、すき家だけでなく、フードチェーン店全体にとって、異物混入リスク管理の重要性を再認識する契機となるべきです。
私たち消費者が安心して食事を楽しめるよう、より一層の意識向上と具体的な対策を期待します。



コメント